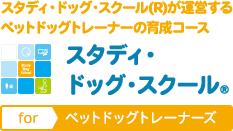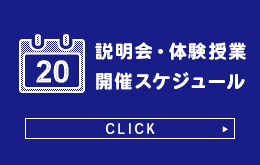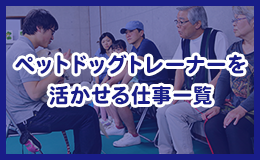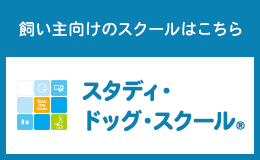最近のエントリー
月別 アーカイブ
- 2025年12月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2025年4月 (2)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (3)
- 2024年2月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (6)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (2)
Topics 9ページ目
卒業生の特典!
1.サーティフィケートの発行
 スタディ・ドッグ・スクールドッグトレーナー育成コースは業界内でも一目置かれる先進的なドッグトレーナー育成学校です。そのスクールを卒業した、優れたドッグトレーナーであることを証明するサーティフィケート(証明書)を発行いたします。
スタディ・ドッグ・スクールドッグトレーナー育成コースは業界内でも一目置かれる先進的なドッグトレーナー育成学校です。そのスクールを卒業した、優れたドッグトレーナーであることを証明するサーティフィケート(証明書)を発行いたします。また、ご自身のホームページに育成コース卒業生バナーを貼り付けるなど、ご活用いただけます。
※サーティフィケートの発行はペットドッグトレーナークラス修了試験に合格し、所定の仮リュラムを終了したに方に限ります
2.独立開業サポート
ホームページ作成や備品購入、必要書類の作成のサポート、その他サービス内容やその価格決定など、開業に伴う準備段階からスタディ・ドッグ・スクールがバックアップいたします。また開業後も広報活動や運営ノウハウなど様々なアドバイスを通して卒業生の成功をサポートいたします。※ペットドッグトレーナークラス受講生に限ります
3.永久に実習が無料
卒業した後でも、履修したクラスの選択実習に無料で参加ができ、ドッグトレーナーとしての技術を磨き続けることが可能です。※卒後の参加はSDS認定ドッグトレーナーに限ります
4.無料の勉強会への参加が可能
 定期的に開催する卒業生を対象とした無料の勉強会にご参加いただけます。勉強会では、当スクールの講師や、先輩ドッグトレーナーなどと一緒にドッグトレーニングに関わる様々なテーマについて思う存分ディスカッションしていただけます。また、webによる参加も可能ですので、遠方にお住まいの方でも気軽に参加することが可能です。
定期的に開催する卒業生を対象とした無料の勉強会にご参加いただけます。勉強会では、当スクールの講師や、先輩ドッグトレーナーなどと一緒にドッグトレーニングに関わる様々なテーマについて思う存分ディスカッションしていただけます。また、webによる参加も可能ですので、遠方にお住まいの方でも気軽に参加することが可能です。5.お仕事を依頼
開業したものの、お客さんがつくまでの期間が収益的に不安であるなど、悩みはつきません。当スクールでは卒業者特典として運営するしつけ方教室や幼稚園、さらには教育機関や各種イベントの講師としての出講を優先的にご依頼し、金銭面でのバックアップもいたします。※SDS認定ドッグトレーナーに限ります
6.「スタディ・ドッグ・スクールの卒業生」、「卒業生の声」への掲載
当スクールの卒業生として「スタディ・ドッグ・スクールの卒業生」、「卒業生の声」、SNSなどで紹介させていただき、開業後の広報活動にご協力いたします。7.主催イベントの広報協力が受けられる
卒業後にご自身が主催するイベントなどの広報を、ホームページやSNSなどを通してお手伝いします。8.セミナー優待
 スタディ・ドッグ・スクールが主催するドッグトレーニングセミナーに優先的にまた優待価格でご参加いただけます。また、多くの動物業界関係者が参加するセミナーを通じてネットワークを広げることも可能です。
スタディ・ドッグ・スクールが主催するドッグトレーニングセミナーに優先的にまた優待価格でご参加いただけます。また、多くの動物業界関係者が参加するセミナーを通じてネットワークを広げることも可能です。9.講師を呼べる
卒業後にご自身の教室などでセミナーやカンファレンスを開催する際には、当スクールの講師が出講しお手伝い致します。10.スタディ・ドッグ・スクール永久会員
当スクールが運営するしつけ方教室スタディ・ドッグ・スクールの永久会員として、様々な特典が受けられます。
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年12月 6日 11:27





ほぼ日さんドコノコのオフ会 講師出講
株式会社ほぼ日さんが運営しているコンテンツ
ドコノコ のオフ会に講師としていってまいりましたぁ。
向かったのは、大阪にある住宅展示場 ABCハウジング 中百舌鳥住宅公園。

住宅公園で、一体何を話したのかというと・・・
犬や猫と人の快適を、住まいの工夫から考える
というお題で、例えば「ピンポン」で吠えてしまう犬には、
住宅の中で、どのような工夫すれば、吠えなくなるのか、
といったことを、住宅を見ながら話をして回る、といったものでした。

みんさんにお会いできて、とっても楽しかったぁ〜


今週末(17, 18日)も大阪にて、同じイベントを開催しますので、
ご興味のある方は、是非、お待ちしております!!
詳しくは、こちらから。
スタディ・ドッグ・スクール
長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年11月13日 17:44





卒業生がしつけ教室をオープンしました
割嵜さんは家庭犬ドッグトレーナーの国際資格であるCPDTーKAを取得されており、安心してワンちゃんをお預けいただけます。
ご自宅を改装したしつけ方教室はアットホームでワンちゃんにとって安心できる環境です。
いぬの幼稚園、個別レッスン、グループレッスン、お散歩代行、ノーズワークレッスン 、ワークショップ・セミナー開催など様々がありますのでご自身のワンちゃんにあったメニューをお選びいただけることも特徴の一つです。
教室では看板犬のジャック・ラッセル・テリア、グート君がお出迎えしてくれます。
オープニングイベントとして11月1日~9日にわんちゃんのチャリティーお悩み相談会を開催しますので、
ご興味のある方はぜひご参加ください。
いぬの幼稚園 dog training at home Gu.uT(グート)
コンセプトは、「みんなが集まり、ワンちゃんたちが学べるくつろぎの場所」。
川崎市宮前区にあるアットホームな一軒家で大切な愛犬の長所を育むトレーニングを!
ワンちゃんたちとの生活がより良いものであるためのサポートをさせていただきます。

(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年10月27日 09:45





卒業生を対象とした勉強会を開催しました
勉強会では、ざっくばらんに各自の抱えている問題や興味のあるポイントなど、積極的な議題の提起や熱い議論を交わしました。
和犬のしつけ、転嫁行動やフード、シニア犬についてなどなど現場の意見が満載です。
卒業後もつながりを持ち、助け合いながら切磋琢磨できる素敵な関係です!
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年10月16日 19:33





愛玩動物飼養管理士のスクーリング講師(仙台)
8月末に愛玩動物飼養管理士のスクーリング講師として
仙台へ行ってまいりました!!
参加者140名ほどと、なかなかの人数ではありましたが、
「動物のしつけ」と題して、学習理論や犬の成長過程、
そして犬のしつけ方について、お話をさせていただきました!
今年は残すところ、あと一回。東京での講義が残っております。
たまに、講義会場で育成クラスの生徒さんに会うこともあり、
そんなサプライズに期待しながら会場に行くのが楽しかったり・・・(笑)。
もし将来的に、スタディ・ドッグ・スクールのペットドッグトレーナー育成コースに
通うことを検討している方がいましたら、是非、お声がけください!!
ドッグトレーナー育成コース講師 長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年9月 8日 16:05





卒業生がメディアに掲載されました
破壊王の子犬が今では仕事の相棒に。私たちが頑張れる元気の源!|愛犬愛猫エピソード
割嵜さんは当スクール卒業後、ドッグトレーナーとして幼稚園や、高校のペットアニマルコース非常勤講師、そして今秋ご自身のスクール「Dog training at home Gu.uT」をオープン予定とマルチに活躍されています。
割嵜さんの「卒業生の声」はこちら→「抱えていたモヤモヤが解消されました」
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年8月23日 09:40





お盆期間のお休みについて
電話、メールでのお問い合わせに関するについて
電話でお問い合わせされた方は、留守番電にご用件をお入れください。
メール返信、資料の発送に関しましては、8/17以降となりますので何卒よろしくお願いいたします。
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年7月23日 14:56





講師のメディア掲載と最近思うこと...
6月は監修した記事や、連載が相次いで公開、掲載されました。
校長の鹿野正顕は「いぬのきもち」の監修をしました。今年に入りすでに3回目と絶好調!

今月はトップの記事など2コーナーに掲載されています。
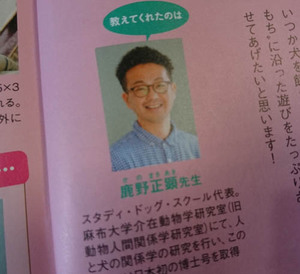
また、座学を担当している三井の「PetLIVES」連載は今月で5年目に突入。

今月は少しマニアックな行動の「教え方」について執筆しています。
どちらも実現不可能な机上の空論や都市伝説的な方法論ではなく、「科学的な根拠」+「のべ10万頭以上の経験」に基づき、なるべく難しい言葉を使わないよう例え話などを用いて執筆しています。
過去の出演や連載はこちら
さて、ペットドッグトレーナー育成コースの授業では、もちろん専門用語を使って難しい話をすることもありますが、全ては「一般の飼い主さんに理解を深めていただけるよう、プロとして本当に伝えたいことを噛み砕いて伝えるための通過点」だと考え、あえて使用しています。(もちろん、ただ難しい定義をお話するだけでなく、その後、実例や例え話を用い、わかりやすい解説、表現を心がけておりますので、難しくてついていけないかもしれないというお悩みは不要です!)。
最近、講師たちが少し懸念していることがあります。ドッグトレーニングにも科学的な視点や手法が取り入れられ、あつい議論が交わされるようになってきました。
これ自体はドッグトレーニングの発展と普及のため、大変喜ばしいことなのですが、それに伴い学術的な用語や高度なテクニックなどが紹介されることも珍しくなくなってきています。
もちろん我々もいちトレーナーとして専門的な話をする時間や、高度な技術の習得や実践、そして愛犬とともに困難な課題をクリアしていく時間は大変貴重で大好きな時間のひとつです。
しかしながら、家庭犬のしつけやトレーニングは「飼い主さんに実践してもらう」ことが大前提。特殊技術やマニアックな知識の習得に躍起になり、飼い主さんが置き去りになることは絶対に避けなければなりません。
難しい話を難しく話したり、小難しく実践することは簡単ですが、それによって犬のしつけやトレーニングがマニアックな方向にシフトし、「なんだかとっつきにくい…」と一般の飼い主さんから敬遠され、実生活からかけ離れたものにならないよう「難しいことをわかりやすく」噛み砕いて表現、実践できるような座学と実技を心がけています。
ドッグトレーナー育成コース講師:三井
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年6月19日 14:10





6期生 8回目の授業 座学:「馴化」、「オペラント条件づけ」 実技:「逐次接近法を用いたマテの練習」
基本的な原理や方法について解説後、動画資料を用い、慣らすべき要素ごとに分類したうえで系統的脱感作と拮抗条件付けについて学びました。
この際、ボディーランゲージを読み取る練習をしたり、時間経過とともに対象になれていく様子を観察しました。
また、理論を身につけると「理論通りにやれば絶対にうまくいく」と思い込んでしまうことですがあります。しかし、いわゆる学習理論は実験室の中で証明されたものでしかありません。
動物は機械ではありませんのでもちろん学習にも限界があります。頭でっかちな理論に溺れないよう、実例を交えつつ授業をしています。
そして、本日からオペラント条件付けについても授業を開始しました。
オペラント条件付けは新しい行動を身につける際や、問題行動修正などにおいて不可欠な理論で、ドッグトレーナーや優れた飼い主になるためには絶対に身につけておかなければならない項目の一つです。
一度聞いただけではなかなか理解しづらい部分ではありますが、質疑応答や生徒さんそれぞれの経験談を含めて分析、解説していくことで理解度を深める工夫をしています。
また、オペラント条件付けはそれぞれのしつけ方教室や流派によるカラーがもっとも反映されやすい部分でもあります。
例えば「ほめてしつける」や「おやつは一切使用しない」などといったそれぞれの方針が、解剖学、生理学、行動学的にどう解釈するべきなのかなども交えて授業をしています。
そして何よりも大切な犬の習性を踏まえた上で、問題に直面している飼い主さんをどうすれば救えるのか柔軟な発想をもって対応できる力を磨いています。
ドッグトレーナー育成コース講師:三井
午後の実習では、「逐次接近法を」もちいた
マテの練習を行いました。
トレーニングを行うときは、人が明確な目標を立て
その犬の学習レベルや進み具合に合わせて
徐々に教えていく必要があります。
「何となく」の教え方では
実は犬が混乱をきたしてしまい、いくらご褒美を与えても
犬にとってトレーニングがストレスになってしまいます。
人がしっかりとした学習の目標と進め方を設計することが
効率よく犬にとってもわかりやすいトレーニングになります。
ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年5月29日 15:48





6期生 7回目の授業 座学:「古典的条件づけ」、「馴化」 実技:「実践的なお散歩の練習」
トレーナーとして必ず身につけ、お客様に噛み砕いて説明し、実行していただくところですので、毎回しつこいぐらい丁寧に授業を行います。基礎ほど大切なことはありません。
トレーニングの本を呼んだり、しつけサイトを調べたりご自分で勉強されている方ほどこんがらがってしまうところですが、ひとつひとつ確認しながら、質問をどんどん吸い上げながら授業を行えるところが少人数制のいいところでもあります。
十数年、飼い主さんや専門学校の学生さんにご説明しているので、講師陣はなぜ理解し難いのか、どこがこんがらがっているから分かりづらいのか熟知しています。
どんどん知識を吸収していってくださり、授業をやる身としても楽しいところです。
そして、今日は馴化の方法について詳しく解説しました。
なにかに馴らすということは、社会化や問題行動改善の上で非常に重要なことですが、経験だけに頼らず、犬の行動をきちんと分析し、それを誘発する刺激や犬の心理状態を推察した上でプログラムを立てていくことが求められます。
このような対処は学問としてある程度方針が決まっており、科学的に裏打ちされた方法が実施することが必要です。
どのような要素に対し、どういった方法を用いて改善を試みればいいか、いよいよ実践に近い内容になってきました。
ドッグトレーナー育成コース講師:三井
午後の実習では、先週に引き続き、「ほめ言葉」、「名前を教える」、「呼び戻し」、「コマンドトレーニングの練習を、幼稚園に参加している犬でも練習をしました。
また、先週行った、歩行の練習を実際のお散歩でも
実践的に活用できるように、外での練習を行いました。
 トレーニングでは、練習の時間を設けて
トレーニングでは、練習の時間を設けて新しい行動を教えますが、実際の生活の中で
練習をした内容を落とし込めるようにしなければなりません。
そのためにも、「基本的な練習」だけでなく
「実践的な対応」についても併せて理解し
実際の生活に応用していく必要があります。
また、本日の実習後、新店舗のお祝いを
6期生の皆様から頂きました!!
 とてもおしゃれな卓上カレンダー!
とてもおしゃれな卓上カレンダー!新店舗のデザインにもぴったりです!!
6期生の皆様、本当に本当にありがとうございました!!
ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野
(スタディ・ドッグ・スクール)
2018年5月22日 17:06





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。