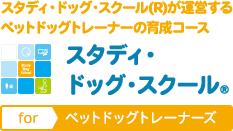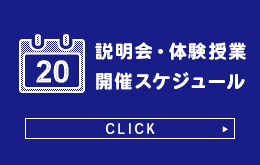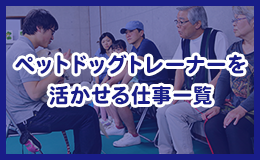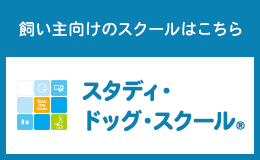最近のエントリー
月別 アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (3)
- 2024年2月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (6)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (2)
HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 9ページ目
Topics 授業の様子 9ページ目
3期生 14回目の授業「犬の問題行動の対処の概論」「トレーニングアイテムの使い方」
ドッグトレーナーとしてどういう姿勢で飼い主さんに臨むのか?どうやって問題行動修正に必要な情報を集めどうアプローチするか、
ドッグトレーナーが遵守すべきルールなど今までの経験を含めてお話しました。
問題行動の原因究明には科学的にアプローチし体系的に解釈・整理することが必要です。
その情報を聞き出すためには飼い主さんや、時には家族全員とのコミュニケーションが大切になります。
情報を聞き出すテクニックや整理する術、問題解決の提案の仕方、注意点などについてもお話しています。
ドッグトレーナーに必要なコミュニケーション&マナーについては例年通りその道のプロである松井かおり先生に講義いただいております。
日曜日に開催した授業の様子はこちらをご覧下さい。
ドッグトレーナー育成コース講師:三井
午後の実習は、前回の宿題からスタート。
「オスワリ」「ホールディング」のトレーニング方法を生徒さんから説明していただきました。

説明後は、講師から「もっとここを詳しく説明したほうが良い!」「話す順番を~~。」
など細かくアドバイスさせていただきました。
その後は、トレーニングアイテムの使い方、メリットデメリットの指導をさせていただきました。
優れた道具も使い方によっては、意味のないものになってしまったりすることもあります。
正しい使い方を知り、理論立ててトレーニングに生かすことがとても大切になります。
ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2017年1月24日 16:38





3期生 13回目の授業「指導スキル」「問題行動の修正」「健康管理の方法」
ドッグトレーナーは犬ができるようにするだけではなく、飼い主さんに犬を扱えるようになっていただいたり、必要な知識を身につけて貰う必要があります。
つまり、人嫌いの犬バカであっては成り立ちません。
ですから、どのように説明すれば相手にわかりやすく伝えることができるか、犬も飼い主も改善するかを常に考えながら指導しています。
相手にものを伝える手段は様々ですが、レッスンの形態によってもその手法は変わることがあります。
今までスクール運営で培ってきたノウハウやテクニックなどをもとに受講者の皆さんにお伝えしています。
また、今回から問題行動の修正への臨み方についても授業を開始しました。
より実践的な内容となり、今まで学んできた知識を総動員して解決を目指すのはもちろんですが、情報収集や問題の体系的にな解釈も必要となります。
専門家としてどうアプローチしていくか今後より深く学んでいきます。
ドッグトレーナー育成コース講師:三井
実習では、前回から行っているトレーニング指導の練習から始まりました。
今回は、「ご褒美の選び方」「ほかの犬や人との挨拶」をテーマ。
まだまだ練習は始まったばかりですが、生徒さんからも自分の中の知識を整理できる!と良い意見をいただいております。
今日はその他に、「オスワリマテ」の状態で人に触られる練習。

急に触るとびっくりして立ち上がってしまうので、近づくところや手を確認させるところ、首を軽くさわる、など段階を追ってトレーニングしました。
生徒さんに犬のボディランゲージを見つつ、刺激レベルを判断していただきながら練習しました。

また、ブラッシングや耳掃除の練習をご自身の犬以外で行いました。
生徒さんは柴犬を飼われているので、トイプードルに四苦八苦していましたが、ポイントを説明すると上手にできました。
色々な犬種を扱うことがとても大切な勉強になります。
ドッグトレーナー育成コース講師:鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2017年1月17日 16:39





3期生 12回目の授業「犬の問題行動」「トレーニングアイテム」「弁別トレーニング」
問題行動は今後各論へと進んでいくためにまずは広く知識を得るところから行いました。
例えば、一口に噛むといってもその原因は両手両足の指の数では足りないほど様々あります。
場合によっては獣医師との連携が必要な場合もあり、何でもかんでもしつけ不足と片付けることはできません。
ですから、まずはどのようなタイプの問題行動に大別されるか知ることが必要です。
後半は「トレーニングアイテム」について。
トレーナー自身が犬をコントロールすることができても、飼い主さん自身ができなければ根本的な解決には至りません。
ですから、飼い主さんが最も効率よく問題を解決するにあたり、何か一番良いかを判断し、場合によってはトレーニングツールの使用を提案できるよう
ドッグトレーナーは様々なトレーニングアイテムに精通している必要があります。
また、トレーニングの現場では使用を嫌悪される道具も、何故嫌われるのか正しく理解していなければただの知ったかぶりになってしまいます。
なぜその道具がよく使われたり、反対に使われなくなってきているのか、数あるトレーニングアイテムのメリット、デメリットをしっかりと説明できるよう入念に授業しています。
スタッフ三井
午後の実習では、前回出した宿題から始まりました。
どのような宿題かと言いますと、生徒さんがトレーナー役になり、トレーニング指導をしていただくというもの!
今日は「褒め言葉」「名前に反応する」トレーニングという基礎的なことを行いましたが、自分で説明するのは難しい!
と生徒さんは少し手こずっているようでした。
(※初めてやったとは思えないぐらい十分できていましたが、、、。)
自分で指導できるようになることで、ちゃんとトレーニングを理解することにつながりますので、今後も頑張っていただきます!
今日はその他に「人の左側につく=サイド」のトレーニング、「集中して歩き続ける=あとへ」のトレーニングを行いました。

生徒さんのハンドリングがどんどん向上し、スムーズにトレーニングができるようになってきました。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2017年1月10日 16:47





3期生 11回目の授業「飼育環境の設定方法」、「犬の問題行動」
先週から座学もより実践的な内容となっています。
今週は社会維持行動に関わる問題に対処するための飼育環境の設定方法や人の対応について講義を行いました。
このあたりのテーマは個別レッスンやカウンセリングでも一番相談を受ける問題の一つですので、
一つ一つ講師の経験や論理的な対処方法や環境設定について丁寧にお話しています。
経験豊富なトレーナーの現場の生の声が聞ける貴重な機会でもあります。
そして出張トレーニングを行うドッグトレーナーに欠かせない「犬の問題行動」に関する授業が今週からスタート。
まずは概論から学んでいきますが今後はより実践的な各論についてもお話していく予定です。
SDSスタッフ三井
午後の実習では、新しいコマンドを教えました。
人の左側につく「ヒール」、足元で落ち着いている「マット」「ゴーイン」。

教え方をデモンストレーションしながらわかりやすく説明しています。
犬は1頭1頭動き方も異なるので、ご自身の犬以外で練習することも大切です。
生徒さんにも、様々な犬種で練習することができて勉強になると、意見をいただいています。

生徒さんの犬、タマちゃん(左)コロちゃん(右)です。
いつも頑張っていますが、あと半分、楽しみながら練習しましょう!
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年12月13日 16:26





3期生 10回目の授業 飼育環境の設定方法
何か飼い主が困る行動をする、いわゆる「犬の問題行動」の原因は様々です。
問題の解決のために何か教え込んだり、やめさせたりしてする方法もはちろん必要ですが、
度を越すと、すべてコマンドで制御し、我慢させればいいといった虐待とも取れるような対応になってしまいます。
また、そもそも犬が学習しづらかったり、馴れづらい環境などの場合は環境要因へのアプローチが必要です。
授業では犬の行動の分類ごとに生じやすい問題や問題を生じさせてしまう人の対応や環境設定、解決方法を
系統立てて説明するとともにm講師の経験や過去の症例などもあわせてご紹介しています。
スタッフ三井
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年12月 6日 14:12





3期生 9回目の授業
座学は衛生管理について。
トレーナーというと犬をトレーニングする人という認識が強く、現場でも意識が抜け落ちやすい項目の一つです。
しかしながら、不特定多数の犬と触れ合ったり、施設を持っている場合は多くの出入りがある場合、
疾病の蔓延を防ぐためには「公衆衛生」の知識を持ち合わせている必要があります。
また、子犬の社会化とワクチネーションプログラムの兼ね合いなど、
連携を組むことのある獣医師が納得できる衛生管理を提供することができるのもトレーナーの実力の一つです。
さらに、飼い主さんにいちばん身近な犬の専門家の一人として、犬の精神的健康や社会的健康にも十分考慮し、アドバイスする必要があります。
授業が進むにつれ、犬のトレーニングだけではない大変重要な項目もどんどん身についてきました。
SDSスタッフ三井
実習は、マテのトレーニングの復習からはじまり、オスワリだけでなくフセやタテの姿勢でもできるようにステップアップしました。

少人数制なので、一人一人細かく指導させていただいています。
自分では気づかないハンドリングの癖などを伝え、トレーニングを客観視しながら行えるように授業を行っています。

さらに、今日はおもちゃの管理方法や選び方を説明し、おもちゃを使った犬との遊びを実戦しました。
まだまだ練習しきれていない部分もありますが、基本的な遊び方、おもちゃの離し方、人の手に歯を当てない方法を学びました。
犬との生活、またトレーニングの中でも重要な遊び、、。とても奥が深いです。
来週からも繰り返し、練習していきます!
最近、スタッフの三井が犬との遊びについて、WEBマガジン「PetLives」にて記事を投稿しておりますので、ぜひご一読いただければと思います。
記事はこちら
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年11月29日 16:34





3期生 8回目の授業
今日の座学は先週に引き続き『健康管理』について。
獣医師から信頼してもらえるしつけ方教室にするためには基本的な健康管理や維持、衛生管理に関する知識が必要になることもあります。
さらに、子犬のワクチンと社会化に関することは獣医師と密接に連携することが必須となります。
そのためには経験だけでなく知識や科学的なデータが必要な場合もありますし、自分の犬の健康を維持するためには日頃の些細な変化に気づくための知識が必要です。
本項ではじっくりと講師たちの経験談を交えつつ現場に即した授業を行っています。
SDSスタッフ三井
午後の実習では、「マテ」のトレーニングから始まりました。
日常生活の中でもよく使う指示の一つですが、基本的な教え方から活用方法まで細かく説明させていただきました。
「マテ」=「マテと言われたときの姿勢を維持し続ける」と、犬に正しく理解させるためには、
おやつを目の前にして動かないように我慢させる方法では教えられません。
簡単なトレーニングですが、犬の気持ちを読み取り、どのように学習しているのか考えながら行うことが大切です。
今日はその他にもおもちゃを使った運動のさせ方や、座学の内容でもあった爪切りの方法も行いました。

SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年11月22日 17:39





3期生 7回目の授業
座学で3週にわたり丁寧に学んできた「犬の学習」については今週で終了。
理論と実践どちらに偏りすぎても困るのは飼い主さんであり、犬です。
SDSトレーナー育成コースでは特定の手法論にこだわるのではなく、使う手法のメリット・デメリットを理論的に把握した上で
その犬ににあった最適な手法を選択できるように授業を行っています。
この後はしっかりと実技の中で理論を実践に活かすすべを学んでいきます。
そして今週から健康管理についてお話しはじめました。
SDSではドッグトレーナーは常に飼い主さんのそばに寄り添える専門家の一人でいたいと考えています。
もちろん犬に関わる各専門家の專門領域を侵しはしませんが、最適な専門家を紹介するために専門分野以外の知識も必要です。
また、日頃のお世話のアドバイザーとしての役割もありますので幅広い分野を学んでいます。
SDSスタッフ三井
今日の実習では、「呼び戻し」の練習を行いました。
飼い主指導のスキルも学んでいただくため、トレーニング方法を説明できるように教えています。

生徒さんには熱心にメモしていただいております。
また、ご自身の犬以外もハンドリングしていただいております。
トレーナーとしてはもちろんですが、犬のことを深く知るためには、
様々な犬種、年齢の犬と触れ合ったりトレーニングする経験がとても大切です。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年11月15日 16:32





3期生 6回目の授業
座学は先週から学習について勉強し始めましたが、
今日は問題行動の修正で特に必要となる脱感作と拮抗条件付けから開始しました。
一言に何かに慣らすと言っても、闇雲にやっていては慣れるものも慣れません。
優れたドッグトレーナーは反応が起きる刺激を評価し、優先順位を決定した上で計画を立て実行していきます。
また、今週はオペラント条件づけについても講義を行いました。
ドッグトレーナーとしては知っていて当然の項目です(もちろんこれだけではだめですが…)。
さらに、オペラント条件付けに影響する要因などについても細かく説明。
実際の現場で注意すべき項目や必ず飼い主さんに説明しなければならない点など科学に裏打ちされた知識とともにお伝えする術まで解説しています。
SDSスタッフ三井
本日の実習では、ハウスのトレーニング復習から始まりました。

手法論を説明し実践を行うのですが、やはり犬という生き物を扱っているので、うまくいかないこともあります。
その時にいかに柔軟に対応ができるのか、知識や経験が試される場になります。
SDSでは机上の知識だけでなく、今までの経験からより実践的な技術が学べます!
一つの手法だけでなく犬によってさまざまな対応が必要であることを生徒には理解してもらいたいと思っています、。
座学では学習についての授業が始まりましたが、実習でも専門用語が飛び交う、少しマニアックな授業になっております。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年11月 8日 15:55





3期生 5回目の授業
早いもので授業開始から1ヶ月が経ちましたが、本日は発達と学習についての授業でした。
発達の授業では復習とパピークラスの開催時に何を重視するのかのについてや、若齢期の大切さと注意点について解説。
特に若齢期は専門書でも触れていない場合があるため、この時期に行動面や内分泌面でどういった変化が出るのかについてお話しました。
後半は学習原理についての授業でした。
学習の原理を知ることはドッグトレーナーには必須の項目です。
もちろん知っているだけでなく使いこなすために現場ではどのような知識が必要なのか丁寧に授業しています。
今日は主に古典的条件付けについてでしたがみっちりと2時間ほど質疑応答を交えながら実施しました。
その場で疑問が解決できるのもSDSトレーナー育成コースの特徴です。
SDSスタッフ三井
実習では、排泄のトレーニングと寝床の設定から学びました。
犬との生活の中で重要な環境設定、またトレーニング方法を説明しました。
一般的に言われている手法論はもちろん、飼い主さんからよく聞かれるお悩みごとへの対策までより実践的な内容を知っていただき、
ドッグトレーナーとして必要な飼い主指導法も実習の中で行いました。

基本的な「オスワリ、フセ、タテ」のコマンドトレーニングも行い、犬を使って座学内容を実践しました。
受講生もどんどんとハンドリングがうまくなっております。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年11月 1日 16:45





<<前のページへ|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|次のページへ>>