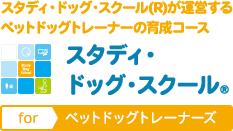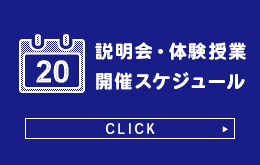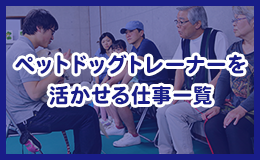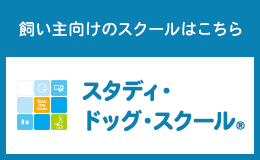最近のエントリー
月別 アーカイブ
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2024年10月 (1)
- 2024年9月 (1)
- 2024年7月 (2)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (3)
- 2024年2月 (2)
- 2023年12月 (1)
- 2023年10月 (1)
- 2023年9月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年7月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年12月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年6月 (1)
- 2022年4月 (3)
- 2022年3月 (2)
- 2022年2月 (2)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (2)
- 2021年11月 (1)
- 2021年7月 (2)
- 2021年4月 (3)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (2)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年2月 (2)
- 2019年12月 (1)
- 2019年10月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年6月 (1)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (2)
- 2019年2月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (2)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (2)
- 2018年9月 (1)
- 2018年8月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (4)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (4)
- 2018年2月 (5)
- 2018年1月 (4)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (5)
- 2017年8月 (6)
- 2017年7月 (6)
- 2017年6月 (5)
- 2017年5月 (4)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (2)
- 2017年2月 (4)
- 2017年1月 (4)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (6)
- 2016年10月 (4)
- 2016年9月 (2)
- 2016年8月 (7)
- 2016年7月 (4)
- 2016年6月 (4)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (3)
- 2016年3月 (2)
- 2016年2月 (4)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (3)
- 2015年10月 (5)
- 2015年9月 (6)
- 2015年8月 (2)
HOME > Topics > アーカイブ > 授業の様子 > 10ページ目
Topics 授業の様子 10ページ目
3期生 4回目の授業
今日の座学は遺伝に関する要因や生理学、解剖学そして行動発達と幅広く実施しました。
レセプターやトランスポーターなどニューロンなどに関する項目は少し複雑ですが、獣医師と連携して行動治療を行う上では
知識としておさえておかなければならない項目の一つです。
生理解剖に関わる知識も犬に関わる専門家としては絶対に必要な項目です。
筋肉や骨格など体の構造や食性、またそれに伴う消化器系などについても講義しています。
また、「殺処分ゼロ」やいわゆる「8週齡規制」において切っても切り離せない、今、スポットライトが当たっている「母子分離」ですが
研究結果をもとになぜ母子分離の時期が重要なのか早いとどのような影響をあたえるのか、
また、あまり知られていませんが遅いとどうなるのかなどについても講義しています。
SDSスタッフ三井
今日の実習では、健康管理の方法を学びました。
動物看護師の資格を持つスタッフ長谷川が、ブラッシングや耳掃除、爪切りなどの方法を指導させていただきました。

授業では、実際に生徒さんにも爪切りを行っていただきます。

耳や爪の構造の話しや、ブラシの種類など細かいところまで説明しました。
生徒さんも積極的に質問したりメモを取っていただき、きちんと理解してくれました。

その後は、環境馴致の練習として、「系統的脱感作法」や「氾濫法」の実践を行い、トレーニング法を学んでいただきました。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年10月25日 16:50





3期生 3回目の授業
授業では犬の感覚器について学ぶことで、同じ刺激を受け取ったとしても人間とは感じ方が違うことなどについてお話しました。
また、犬の脳の構造や神経伝達物質といった情報処理について少しマニアックな項目についても学びました。
少し堅い内容ですが受講生は真剣そのものです。
なぜそんなに細かいところまで学ぶ必要があるのかと思われるかもしれませんが、
犬が何ができて何ができないか知ることは、人間の物差しという先入観を持たないようにするためにはとても重要で、誤った擬人的な考えを防ぐことにもつながります。
SDSスタッフ三井
今日の実習では、犬の行動の作り方「反応形成」の話しから、始まりました。
ルアーを使った誘導法だけじゃなく、誘発法や鋳型法なども含めて、メリット・デメリットなど説明いたしました。

聞くだけではわかりづらいことを、犬で実践することでちゃんと理解してもらいます。
そのあと、犬への指示の教え方にも発展して練習し、トレーニングの全体像をちゃんととらえられる内容となっています。
最後には、環境馴致トレーニングの説明し、来週の実践に続きます。
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年10月18日 17:22





第3期生 2回目の授業
本日もやはり基礎的な項目からスタート。
トレーナーが勉強する行動学というと真っ先に学習理論が浮かぶかもしれませんが、学習理論は行動学のほんの一部に過ぎません。
犬の正常な行動を理解しなければ何が異常な行動なのか?何が問題となっているのか?の原因も特定できませんのでSDSトレーナー育成コースではみっちりと基礎を固めます。
写真:まずはイヌの正常な行動を理解することから。
そして、脳や感覚器の話を交えつつ刺激の処理について解説。
目で見ることのできない処理過程の話なのでので小難しいところもありますが、
認知科学や解剖学的な知識を学ぶことで、きちんとした科学に基づいた視点で動物の行動を理解することができるようになっていきます。
ただただ淡々と基礎をやるのではなく講師の経験を理論に基づいて説明するので、受講者からは毎回「目からウロコだらけ!」と嬉しいお言葉をいただいています。
これからも座学を学び、手法論を理論的に身につけ実践に応用できるよう進めていきます!
SDSスタッフ三井
実習では、先週の復習から始まりました。
「なぜ」この練習をするのかという目的や、練習方法を生徒さんと会話をしながら行いました。
一度聞いただけでは、どうしても忘れてしまうので、生徒さんにも説明していただきながら復習しています(*^^)v
今日は、ホールディングや人と犬とのあいさつの練習。
伝えることが多く、じっくりと説明させていただきました。

座学で学んだことをちゃんと実際に生かるようにすることが大切!
まだまだはじまったばかりですが、みなさんどんどん上手になってきています!
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年10月11日 17:20





第3期生授業開始
2期生はすでにプロとして活躍されているかにご参加頂きましたが、
3期生はより「犬に関する知識を深めたい」ということでSDSのグループレッスンにも参加いただいている一般の飼い主さんが受講されています。
ただ技術や知識を詰め込むのではなく、学術に基づく科学的な知識を基礎から学び、なぜそれが必要なのか、
それをどのようにしつけやトレーニングに応用していくのか実技で実践していきますので、難しくて理解ができないということはありません。
第1回目の授業ではレクリエーションから始まり、
どのようなトレーナーが必要とされているのか、トレーナーがやらなければならないことは何かについてお話する「ドッグトレーナーのMission Statement」の講義と、
「犬の行動特性」についての座学を行いました。
講義では必要な基礎知識と教科書には載っていない実践での応用や研究結果など最新情報を交えながら実施しています。
SDSスタッフ三井
実習には、ご自身のワンちゃんを連れてご参加いただきます!
座学で培った知識をご自身にワンちゃんすぐに生かせる内容となっています(*^^)v
今日は、「スクールの中で落ち着けるようにする練習」や「褒め言葉の練習」などをしました!

盛り上がってしまい、話しが長くなった部分もありましたが、、、(-_-;)
楽しくわかりやすくなるよう頑張っております!
今日は初回でしたが、参加者の方とおしゃべりしつつ、和気あいあいと授業が進みました!
SDSスタッフ 鈴木
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年10月 4日 17:13





第2期生 最終授業
ペットドッグトレーナー育成コース
2期生の授業
早いもので、本日最後の授業が
無事、終了いたしました!
2期生は、すでに現場に立たれている
トレーナーの方々にご参加いただき
普段なかなか話す機会がない
同業での悩みや工夫、スキルなどを
ざっくばらんに包み隠さず話し合えることができたので
私も本当に勉強になり、刺激をいただき
自分自身も見つめなおし、考え直す良い機会を頂きました!
本日最終の授業では
獣医師、石川先生による
「獣医師としてドッグトレーナーに求めること」
というテーマで講義していただきました。
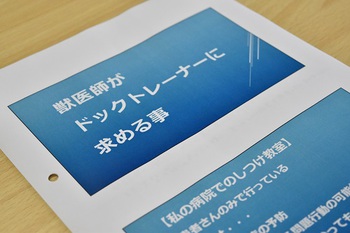

他業種ではあっても、同じく犬に関わる専門家として
互いに連携をしていくことは、飼い主さんにとってもワンちゃんにとっても
非常に重要なことです!
そのためには、相互の理解を深める必要があります!
獣医師の目線から、トレーナに求める生の声は
なかなか聞くことができません!
そのほかの授業として、トレーナーは飼い主さんを対象に
指導をすることが多いですが、本当に
飼い主さんとワンちゃんの幸せな生活を目指すためには
これからワンちゃんを飼う方への指導も大切になります!
今日の授業では、これから犬を飼う方への
指導のポイントを学び、実際の指導する場を現実に
増やしていくためにディスカッションも行いました!!


今日で授業は最後になってしまいましたが
本当に、いつも最後は寂しくなってしまいますね。。。
しかし!これで関係が終わるわけではなく
人と犬のより良い共生社会を目指す仲間が増えたので
今回、ご参加いただいた受講生の皆様と
より密な関係を築き、さらなる躍進を目指します!
SDSスタッフ 鹿野
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年9月 6日 18:13





第2期生の第20回目の授業の様子
特別講師の松井かおり先生の授業でした。
松井先生は、先日行われたJAPDTのカンファレンスでもお話しされた講師で、
既にドッグトレーナーとして活躍されている方対象にも講習をされております。
ただ『オスワリ』を教えたり、『フセ』を教えるだけでは、ドッグトレーナー失格で、
きちんと目的を伝え、飼い主さんにモチベーションを持ってもらったサービス提供をすることがとても大切です。
モチベーションを持ってもらうためには、伝え方が重要です。
そこで、ペットドッグトレーナーになる人は、このような授業を通して知識を身につけることが大切です!!
そして、実技ではクリッカーを使ったフリーシェイピングで、Heel(左側につく)をトレーニングしました。
トレーニングの手法にはいくつかあって、誘発法や誘導法、そして逐次接近法などなど・・・・
全ての手法を理解して、各犬や人に合ったやり方を提供することが重要です。
クリッカートレーニングは、逐次接近法を理解するのにとても適した手法のため、
トレーニングに携わる人は、知っておくべき内容になります。
現在、ペットドッグトレーナー育成コースでは第3期生を募集中です!!
これからドッグトレーナーを目指す方、既にドッグトレーナーをされている方、
特に仕事にするつもりはないけど、犬のことをもっと学びたい方、などなど。
全ての方に、学んでいただける内容です。
まずは、資料請求してください!! →こちらから。
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年8月30日 17:33





第2期生の第19回目の授業の様子
本日の座学では、効果的なホームページ作成について、
外部講師の千田先生に授業をしていただきました。
今の時代、インターネットを駆使した顧客獲得は必須です。
そのためには、SEO対策を熟知した上でHPの作成や更新をしていかなければなりません。
授業は、笑が起きるほど和やかな雰囲気で行われました。
そして本日の実技では、クリッカーを使った少し複雑なシェーピングについて学びました。
コーンをターゲットにした「前へ!!」のトレーニング。
遠隔のトレーニングの1つの手法ですが、原理を知っておけば「右へ」「左へ」と犬を遠隔することができます。
トレーニングの原理原則を知っておくことで、トレーニングのHow toにこだわらず、自分で新しい手法を生み出すことができます。
クリッカートレーニングは、そんなトレーニングの原理を学ぶのにとっても便利な道具です。
そんな、面白い授業が目白押しの第3期生の授業が、10月から開講になります!!
まずは、お問い合わせください!! →コチラから
SDS スタッフ 長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年8月23日 17:38





第2期生の第18回目の授業の様子
問題行動の修正について
カウンセリングのロールプレイを実施しました。
実際の症例をもとに、受講生の方にカウンセリングを
行ってもらい、問題となる行動の
・行動学的解釈と原因の分析
・短期的、長期的な問題行動の管理方法
・行動修正を目指したカリキュラムの作成
を行っていただき、これらの内容に関して
みんなでディスカッションを行っていきました。
実際の症例をカウンセリングし、分析することで
より、修正方法の幅が広がり
実践に近い手法を身に着けることができました!


SDSスタッフ 鹿野
本日の実技は、クリッカートレーニングについて学びました。
実は、私、長谷川は、アメリカの介助犬団体にて
このクリッカーを使った介助犬の育成を経験してきており、
アメリカから帰ってきた当初は、かなりのクリッカーマニアでした。

クリッカーを使う場合、ルールをしっかりと決めてから練習に臨む必要があります。

そして、人も犬のこの学習のさせ方、仕方を理解することで、
学習のスピードがどんどん早くなっていきます。
迷わずタイミングをつかんで『クリック!!』したとしても、
ちょっとずれるだけで、予期せぬ行動をし始めてしまうクリッカートレーニング。
でも、犬が考えている様子や、苦労してやっとできた時の感動は、
他では味わえないものです。
今日は、そんなクリッカーの原理について学びました。
トレーニングを、理論的そして科学的に学びたい方は、参加必須です!!
是非、説明会 or トレーナー交流会にご参加ください。
みなさんとお会いできることを、楽しみにしております。
SDS スタッフ 長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年8月 9日 15:34





第2期生の第17回目の授業の様子
問題行動に取り組む際のカウンセリング方法
について学びました。
本日は、問題行動の中でも攻撃行動について
焦点を当て、
・飼い主からの情報の収集の仕方
・問題行動に対する潜在的な獣医学的原因の評価
・情報から得られる行動学的原因の評価(行動の診断)
・飼い主への教育方法
・適切な行動修正プラン
などの方法を学んだあとで、
実際に、受講生が経験した症例について
参加者みんなでディスカッションを行いました!


自身が担当した症例について
他のトレーナー同士でディスカッションする機会は
なかなか持てません!
しかし、様々な視点やアイデアで一つの症例を考えていけば
より、効率的で飼い主さんにとっても犬にとっても
より良い対策を考えることができます!
本日も、とても貴重な機会が得られました!
SDSスタッフ 鹿野
本日の実習では、
・リードに頼らないトレーニング
「オスワリ」という時に、クセでリードを引いてしまう。犬の名前を呼ぶ時に、同じくリードを引いてしまう。
といったように、無意識のうちにリードに頼ったハンドリングをしてしまいがちです。
犬とより良い関係づくりをするのに大切なのは、リードに頼らないハンドリングをする、ということです。
・「マテ」の解放の合図を教える
「マテ」の後、「いい子」と言って解放していませんか?
「マテ」の初歩的なトレーニングをしている時は、これでもいいのですが、
徐々に「マテ」のレベルを上げる時には、途中で誉め言葉をかけた方が、きちんとした学習をすることができます。
そのためにも、きちんと「よし」などの解放の合図を犬に理解させることが必要です。
・飼い主さん以外からのハンドリング
動物病院に犬を預けた時や、もし地震が来た時に飼い主さんが命を落としてしまい、犬が他の人に飼われる時など。
(地震は来てほしくないですし、命を落とすなんて考えたくもないですが・・・)
慣れていない場所で、慣れない人にハンドリングされる時、
犬たちがストレスを受けないようにトレーニングをして、有事に備えることが必要です。
といった、トレーニング方法や飼い主さんへの伝え方について学びました。
この他にも幾つかの項目について学びましたが、全て書くと長〜〜くなってしまうので、
是非、見学に来てくださいね〜〜。
なお現在、
【聞けば悩みが解消する!ドッグトレーナーのお仕事説明&見学会】
【垣根をぶっ壊せ!ドッグトレーナー交流会】
の参加募集が開始となりました。
どちらも参加無料で、軽食付きですので、お気軽にご参加ください。
参加申し込みは、こちらからどうぞ。
SDS スタッフ 長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年8月 2日 16:56





第2期生の第16回目の授業の様子
問題行動に取り組む際のカウンセリング方法
について学びました。
2期生の方々は、すでにトレーナーとして
活躍されている方々なので
実際に、自身が担当している症例をあげてもらい
・飼い主からの情報の収集の仕方
・問題行動に対する潜在的な獣医学的原因の評価
・情報から得られる行動学的原因の評価(行動の診断)
・飼い主への教育方法
・適切な行動修正プラン
などについて、トレーナー同士でディスカッション
をしながら、それぞれの指導方法の情報交換や
普段行っている指導について、理論的に
再構築する機会が得られました!
トレーナー同士で、互いの指導スキルについて
情報交換したり、ディスカッションする機会は
なかなかありませんが、業界の発展のためには
横のつながりを深め、互いに切磋琢磨していく必要があります!
SDSスタッフ 鹿野
ハンドリングの上手な人は、犬の意識がどこに向いているのか、
今の犬は、どういう感情を抱いているのか、を読み取ることに長けています。
このLeave it を、早めにかけるトレー二ングは、
ハンドリングレベルを上げるヒントになります。
誘惑物のなかでのハンドリグ技術の向上や、


怖い音がした時の対処法方について学びました。
ドッグカフェなどで、ウェイターさんがお盆を落としてしまった!!
そんな時に、ゆっくり過ごしていた犬が『びっくり!!』して飛び上がってしまった。
こういった経験をそのままにしておくと、ドッグカフェに行くのが嫌いなワンコになってしまうことも・・・
そうならないための対処法法を学びました。
SDS スタッフ 長谷川
(スタディ・ドッグ・スクール)
2016年7月26日 15:14





<<前のページへ|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|次のページへ>>