Topics
5期生 7回目の授業 座学:「古典的条件付け」 実技:「逐次接近法:マテの練習」 click to collapse contents
本日は、5期生の7回目の授業
前半の講義では、
「古典的条件付け」
について講義しました。
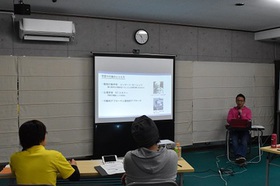 今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる
今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる
学習についての講義が始まりました。
学習といってもその種類は多岐に渡り、犬という動物が
どのような学習によって行動を習得するのか理解を深める必要があります。
特に、感情をコントロールすることが苦手な犬は
古典的条件付けを用いた感情が伴う学習を考慮してあげることが
非常に重要となり、望ましい行動にご褒美を与える正の強化のみでは
感情が伴う問題行動などを修正することは非常に困難となってしまいます。
また、犬が示す行動の要因は、学習のみが影響しているのではなく
様々な要因が関わってきます。
学習によって行動を変えるような機会でも、そのほかの認知的な要因や
日頃の生活環境なども併せて考慮する必要があるため
講義の中では、例を挙げながら学習面でのアプローチ以外の
アプローチ方法も説明し、犬の行動を多角的に分析する方法を学びました。

午後の実技では、前回までの復習と共に
散歩など、犬と一緒に歩く時の「歩行の練習」
逐次接近法を用いた「待て」の練習を行いました。
 屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるため
屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるため
トレーニングの中でも非常に難しい内容の一つであります。
そのため、様々なシチュエーションを想定した歩行の練習が必要となるため
実際の散歩をイメージした練習を行いました。
また、複雑な行動を教える際や、段階をおって少しずつ学習を進める際に用いられる
「逐次接近法」も学び、徐々に目標に進めていく
「待て」の練習を行いました。
 一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など
一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など
明確な目標をイメージして系統立てて教えていく必要があります。
そのため、感覚的に教えるだけでなく、きちんとしたトレーニング
計画を持つ必要があります。
ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野
前半の講義では、
「古典的条件付け」
について講義しました。
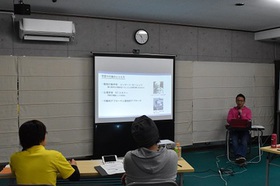 今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる
今週から、いよいよドッグトレーニングや行動習性に必要となる学習についての講義が始まりました。
学習といってもその種類は多岐に渡り、犬という動物が
どのような学習によって行動を習得するのか理解を深める必要があります。
特に、感情をコントロールすることが苦手な犬は
古典的条件付けを用いた感情が伴う学習を考慮してあげることが
非常に重要となり、望ましい行動にご褒美を与える正の強化のみでは
感情が伴う問題行動などを修正することは非常に困難となってしまいます。
また、犬が示す行動の要因は、学習のみが影響しているのではなく
様々な要因が関わってきます。
学習によって行動を変えるような機会でも、そのほかの認知的な要因や
日頃の生活環境なども併せて考慮する必要があるため
講義の中では、例を挙げながら学習面でのアプローチ以外の
アプローチ方法も説明し、犬の行動を多角的に分析する方法を学びました。

午後の実技では、前回までの復習と共に
散歩など、犬と一緒に歩く時の「歩行の練習」
逐次接近法を用いた「待て」の練習を行いました。
 屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるため
屋外を歩く「散歩」は、様々な誘惑や刺激があるためトレーニングの中でも非常に難しい内容の一つであります。
そのため、様々なシチュエーションを想定した歩行の練習が必要となるため
実際の散歩をイメージした練習を行いました。
また、複雑な行動を教える際や、段階をおって少しずつ学習を進める際に用いられる
「逐次接近法」も学び、徐々に目標に進めていく
「待て」の練習を行いました。
 一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など
一言に待てと言っても、時間的な要素や飼い主との距離など明確な目標をイメージして系統立てて教えていく必要があります。
そのため、感覚的に教えるだけでなく、きちんとしたトレーニング
計画を持つ必要があります。
ドッグトレーナー育成コース講師:鹿野
